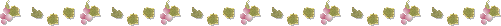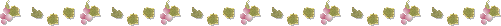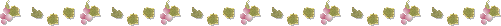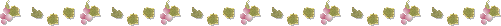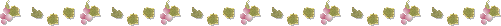偽書「ナイトメア」シリーズ
[ロシュフォール] [リシュリュー]
[トレヴィル]
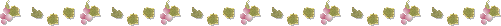
「チェスをしませんか、先生」
「何が望みだ」
「え?」
「呆けた顔で聞き返すな。私に何をさせたい」
「うう…どうしてわかったんですか」
「貴様の下心くらいわかる。
そして、貴様のチェスの腕では私に勝つことなどできないこともな」
「……そう…ですか」
「してほしいことがあるなら、はっきりと言え。
貴様がどうしてもと言うなら、聞いてやらんこともない」
「先生、ありがとうございます!」
「まだ、いいとは言っていな「はい、これです」
「この本が…どうかしたか」
「読んで下さい。なかなか眠れなくて、先生の声で読んでもらったら、
きっといい夢が見られると思ったんです」
「……貴様、チェスなどしたら、ますます目が冴えて眠れなくなるとは
考えなかったのか」
「あ…そういえばそうですね」
「フン…。ベッドに入れ」
「え?」
「回りくどいやり方などせず、最初から本を読んで下さいと頼めばいい」
「はい」
「もう少し奥に行け。私の座る場所がない」
「あの…椅子に座らなくてもいいんですか」
「今は夜だ。離れた所から声を張り上げて読めという気か」
「……いいえ」
「しおりが挿んであるな。ここからでいいのか」
「はい」
「目を閉じろ。読むぞ。
――シスターは言った。『あなたは何を怖れているのです。
私たちを隔てるのは』……」
(あ…先生が黙っちゃった。内容が気に入らないのかな…。
何だか目を開けるのが怖いけど…。う…こっちを見てる)
「貴様は、こういう話を聞きながら眠れるのか」
「は…はい」
「そうか」
「はい…あの……」
「貴様に一つだけ教えてやろう。ここに書かれていることは、読むものではない」
(わっ! 先生の顔が近づいてくる)
「……するものだ」
「▼◇●◎×っ!!」
「フッ…貴様、今何と言った」
「え、ええと…その……自分でもよく分かりません」
「少なくとも人語には聞こえなかった。
だが、貴様の驚いた顔もなかなかの見ものだった」
「あ…あの……」
「その顔に免じて今夜はここまでにしておく。
気が向いたら続きをまた読んでやろう。それまで本は借りておく。いいな」
バタン…。
(あ…先生…行っちゃった。本、持って行ったけど、気に入ったのかな)
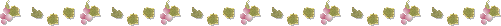
「本を読んでほしいというのだな、ダルタニアン」
「理事長にこんなことお願いするのは何だか気が引けるんですけど」
「いや、気にしなくてよい。いや、これはむしろ喜ばしいことであるな。
お前は遠慮しすぎるのだ、ダルタニアン。もっと私を頼ることだ」
「はい、ありがとうございます。ええと、この本なんですけど」
「うむ。『慎ましき修道女のナイトメア』…か。山場からでよいのだな」
ぱらぱらぱら…
「あ、その辺りから読んでいただけますか?」
「よいぞ。……む? これは、ううむ…」
リシュリューは難しい顔をして黙り込んだ。
「あの…シスターのお話は、やっぱりよくなかったですか」
「そうだな。これは私が読むにはふさわしくない」
「ご…ごめなさい!」
リシュリューは驚いたように本から顔を上げた。
「なぜお前が謝るのだ」
「だって私、失礼なことをお願いしたってことですよね…」
「それは違うぞ。よいかダルタニアン、この本のテーマは背徳である」
「は???」
「だが、清らかな修道女の葛藤と変貌、甘美なる歓びの解放に関する描写が
稚拙すぎる。文章は陳腐にして冗長。これでテーマを描ききれると思うか」
「すごいです…! ぱっと見ただけで、そこまで読み込めるなんて」
「私にとっては造作もないことだ。だが、お前からの素直な賞賛は
特別に喜ばしいぞ。ではダルタニアン、ペンと紙をこれへ」
「はい、どうぞ。あの、何を書くんですか」
「ふふふ…。生ぬるい部分を書き直すのだ。私がお前のために読む一節は、
最上のものでなければならぬからな」
しーーーーーーーーん
さらさらさらさらさら
「さあ、できたぞダルタニアン」
「ZZZZZZZZZ……」
「……眠ってしまったか」
「ZZZZZZZZZ……」
「可愛い顔をして眠っておる。少々残念ではあるが、今宵はもう、
朗読は必要ないようだな。私は帰るぞ、ダルタニアン」
「ZZZZZZZZZ……」
「では、この本は借りていくとしよう。
実は、少々興が乗ってきたのだ。
次回は、驚くほどパワーアップした『慎ましき修道女のナイトメア』を
読み聞かせてやろう。楽しみにしているがいいぞ、ダルタニアン」
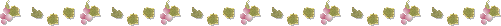
※ ギャグではありません
凍てつく冬の夜。
空には月もなく、ガタガタと窓を揺らす風音ばかりが耳につく。
深夜にノックの音がした。
「はい?」
「私だ。トレヴィルだよ。
入っていいかい、ダルタニアン」
「どうぞ」
今この島には二人しかいない。
なのに、こんなやりとりを繰り返してしまう。
何のためになどという問いは無意味だ。
切り取られた束の間の時間の中では……。
ダルタニアンは読んでいた本を閉じて脇に置き、
少し微笑んでトレヴィルを見上げた。
「眠れないの、ダルタニアン?
灯りが漏れていたから来てみたけど」
「はい。風の音でなかなか寝付けなくて…。それで、本を読んでいました」
トレヴィルは、その本を手に取った。
「深窓の令嬢のナイトメア」――本の装丁に見覚えがある。
人気のシリーズなのか、
女子生徒が持っているのを、よく目にしていた。
内容も少しは知っている。
ぱらぱらとページを繰ると、
この本も似たようなものとすぐにわかった。
「ちょっと扇情的なお話だね」
「あ…そう…だったかもしれません」
少し驚いたように、ダルタニアンは答えた。
……文字を目で追うことしか、していなかったんだね、
ダルタニアン。
読んであげようか―――そう言いかけて、トレヴィルの口からは別の言葉が出た。
「おいで、ダルタニアン。音楽室へ行こう」
「え? 今からですか?」
「眠れない恋人のために音楽を捧げようと思ってね。
私のピアノを、また聴いてくれるかい?」
ダルタニアンの顔が、ぱっと輝き、
トレヴィルの胸がずきりと痛む。
「寒いから毛布を持っていこう。灯りは君が持ってくれる?」
「はい。毛布にくるまって先生のピアノが聴けるなんて、とても贅沢ですね。
夜更かししていてよかった」
「暗いから手をつないで行こう、ダルタニアン」
しかし素直に手を差し出したダルタニアンは、指先が触れ合うと、さっと手を引っ込めた。
「どうしたの? 私と手をつなぐのがいやなの、ダルタニアン」
「私の手が冷たいからです。
これからピアノを弾くのに、先生の手を冷やしてしまったら…」
トレヴィルの手が、ダルタニアンの手をそっと包んだ。
「恋人同士はね、こんな寒い日は互いに暖めあうんだよ。
そうじゃない? ダルタニアン」
頬を少し赤らめて、ダルタニアンは頷いた。
いつの間にか、風が止んでいる。
暗く冷えきった音楽室に、ぽつんと一つ、灯りが置かれた。
窓が淡く光っている。
それは曙光でもなければ、青い月光でもなく……
「雪が、また降ってきました」
ピアノの隣で毛布にくるまったダルタニアンが、窓を見上げて言う。
「春は遠いね」
ピアノの蓋を開けながら、トレヴィルが言う。
「もうすぐですよ」
ダルタニアンは、にこっと笑う。
象牙色の鍵盤に、トレヴィルの白い指が触れ、
ゴルトベルク変奏曲の静謐なアリアが始まる。
自分には訪れることのない春を
君はもうすぐだと言う。
君の言う春は、私の春。
もしも君が春の空を…森を…海を描いたなら、
どんな絵になるんだろう。
暖かな陽射しの中を君と一緒に歩いたなら、
どんなに楽しいことだろう。
緩やかに歩む旋律が、切ないトリルと共に
高みに上り行き、あえかな吐息と共に降りてくる。
ダルタニアンは毛布の前をぎゅっとかき合わせてうつむき、目を閉じた。
音楽は、祈りに似ている。
いや、祈りそのものなのかもしれない。
祈ることを許された人間にとっては…。
ありがとう、ダルタニアン。
私の音楽を、全身全霊で、受け止めてくれるんだね。
私は君に、最期の思い出を作ってあげるはずだった。
なのに、いつの間にか君が私に思い出を作ってくれている。
私は君の心からの笑顔を…幸福な笑顔を見たいと願ってしまった。
君からそれを奪ったのは私なのに……。
島を覆う暗い空から雪は絶え間なく降り続け、
窓枠はいつの間にか白く縁取られて、
ガラスに氷の花が咲いている。
春は、遠い。
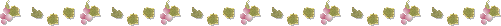
| GUIDE
| TEXT
| BOOK |