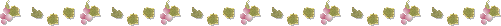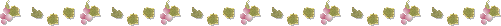ある早春の夜
ポルトス×ダルタニアン
しんと静まりかえった夜の生徒会室に、ダルタニアンがペンを走らせる音だけが聞こえている。
卒業まであと1ヶ月余り。ダルタニアンの銃士隊隊長としての職務は、多忙を極めていた。
一年間の生徒会活動を取りまとめて報告書を作りながら、通常の仕事も続けているのだ。
生徒達からは、年度末などおかまいなしに、毎日のように問題が持ち込まれる。
さらに時期銃士隊への引き継ぎ準備があり、間もなく卒業試験も始まる。
ペン先が軋んで進まなくなり、ダルタニアンは手を止めた。
そこで初めて、原因はペンではなく、自分の手がかじかんでいたためだと気づく。
「あ…もうこんな時間。でも、もう少しやっておこう」
春浅いこの時期、まだまだ夜は寒い。だが、今から部屋を暖めることもない、と
ダルタニアンはコートを引き寄せると肩に羽織った。
その時、廊下で大きな足音がした。と、ノックもそこそこにポルトスが飛び込んでくる。
「ポルトス、どうしたの?」
「お前こそ、ここで何やってんだよ!
お前の部屋に行ったらもぬけの殻で、探したんだぞ」
「ごめん。でも、残って仕事するって言わなかったっけ?」
「それ何時のことだと思ってるんだ?」
「ええと…確か……ううん、忘れた」
「あーっ! もうこれだからお前は」
「で、ちゃんと勉強はできたの?」
「え…?」
「卒業試験が近いから、勉強がんばるって言って帰ったんだよね」
「……か、関係ねぇだろ! てか、お前、こんなに仕事が残ってたんなら、オレに一言言えよ」
「でもポルトスは、自分の仕事ちゃんと終わらせたんだし」
「だいたいコンスンタンティンはどうしたんだよ。次期隊長なら一緒に残って
お前のこと手伝っても……いや、だめだ! それは絶対だめだ!」
「?」
「わわわ! きょとんとした顔すんじゃねぇ! 可愛いすぎて困る…」
「ねえ、ポルトス」
「な、何だよ。急に真顔になるなよ。ますますドキドキするじゃねぇか」
「私を探してたんだよね。仕事はもうじき終わるから、安心していいんだよ」
(きょとんとした顔がだめって言うから、真面目な顔したのに、変なポルトス。)
「そ、そういうことじゃねぇんだよ。お前、夕食、ちゃんと取ったのか?」
「あ……忘れてた」
その途端、ダルタニアンのお腹から、くぅぅぅっ!……と音がした。
「!」「!」
二人は顔を見合わせ、同時に笑い出す。
「お…お前なあ…空腹に気がついたとたんに腹が鳴るって、正直すぎるだろ」
「ふふっ…あんまり女の子らしくなかったね」
「そうか? お前らしくて、いいぜ」
そう言いながら、ポルトスは手に持っていた籠をダルタニアンに渡した。
「こんなことだろうと思って、食堂からめぼしいもん漁ってきたんだ」
「ありがとう、ポルトス」
ダルタニアンはパンにチーズを乗せて左手に持ち、右手でペンを取った。
しかしその手から、ポルトスが素早くペンを取り上げる。
「食事の時くらいちゃんと休めよ!」
珍しく真剣な様子で声を荒げたポルトスに、ダルタニアンははっとした。
「……そうだね、ごめん。いただきます」
そしておとなしく書類を脇に寄せて、パンを口にする。
「悪ぃ、大きな声出しちまって。…スープもあるぜ」
「…ありがとう」
冷たい夜風が、窓をカタカタと鳴らした。
黙々と食事をするダルタニアンの傍らで、ポルトスは落ち着かない様子で机の端に腰掛け、
決裁書類の山を見た。
「すげえな…この量」
「うん。今さらだけど、アトスさんてすごかったんだって、しみじみ思うよ」
「そうか? ヤツもよく遅くまで残ってたけどな」
「だって、アトスさんの仕事は完璧だもの。去年の書類を見るたびにため息が出るくらい。
その上、忙しい銃士隊の仕事をきちんとこなしながら私に協力してくれたでしょう。
それがどれだけすごいことなのか、今になって、やっとわかったんだ。
私だったら、急に飛び込んできた生徒に、アトスさんみたいに対応することなんて、できなかったと思う。
でもアトスさんには及ばないけど、私もアトスさんを目標に努…」
ガタン! と音をさせてポルトスは机から飛び降りた。
そのままダルタニアンの前まで来ると、その腕をぐいっと掴む。
「やめろよ!! さっきからアトスアトスって!」
「え?」
驚いて顔を上げたダルタニアンと目が合い、ポルトスの勢いが少し削がれる。
「あいつは…まあ確かに凄いヤツだけどさ、比べても仕方ねぇだろ。
第一、オレの前で他の男の名前なんか連呼するなよ」
「ポルトス、どうしたの? 何だかいらいらしてるみたい。ポルトスらしくないよ」
「見てられねえからだよ! お前ってさ、いつもそうだろ?
自分が頑張ればいいと思ってるだろ? でも知ってるのか、お前…少し痩せたぞ」
ダルタニアンは、ゆっくりまばたきした。ポルトスの苛立ちの原因がわかったのだ。
「ごめん…。心配…してくれたんだね。でも大丈夫だから」
「大丈夫じゃねぇから心配してるんだろうが!
昨日お前にキスした時、肩も背中も薄くなってるのに気づいたんだ」
「女の子としては、太るよりいいと思うんだけど」
「バカッ! 倒れたらどうすんだよ! お前が病気にでもなったら…
もちろんオレがきっちり看病して絶対治してやるけど、
……一番つらい思いをするのは、お前だろ?」
「ポルトス……」
ポルトスはダルタニアンの肩を引き寄せると、そのまま抱きしめた。
「なあ、オレって、そんなに頼りないか? オレには何も任せられないのか」
くぐもった声が、腕の中から答える。
「ううん…そんなことない」
「だったらもっと甘えろよ」
「ありがとう、ポルトス。でも、私、すごく助けてもらってるんだよ。
ポルトスが一緒にいてくれたから、ここまで来られた。
ポルトスが支えていてくれるから、銃士隊の隊長として最後まで揺るがずに頑張れる。
私、もうポルトスにいっぱい甘えてるから……ありがとうね、ポルトス」
「うおおおおおおおっ!」
「?」
「こ…こんな可愛いこと言われたら、オレもう、ガマンできねえ!! ダルタニアン!!」
その時、部屋の時計が時を報せた。
ダルタニアンはポルトスの腕をすり抜けて、ぱっと立ち上がる。
「ポルトス、聞こえた? もうすぐ消灯時間だよ」
「へ?」
「部屋に戻らなきゃ」
「お、お前、せっかくいい感じだったのに、切り替え早っ…」
「はい、これ」
「何だ、この書類は」
「書き終わった分。学校への提出用の箱に入れてくれる?」
「お、おう。で、そっちの書類の束は何なんだ?」
「こっちはまだ目を通してないの。これから持って帰って続きを」
「よしっ! じゃあキマリだ。オレにも手伝わせろ、いいな。
この書類もらってくぞ」
「え? でもそれ、ちょっと面倒な確認が必要なんだよ」
戸惑うダルタニアンに、ポルトスは笑って宣言した。
「明日の放課後には、きっちり仕上げて持ってきてやるよ。
オレの方が銃士隊の経験は長いんだ。心配すんなって。消灯までもう時間がない。
部屋まで送るぜ。だがおやすみを言うまで、今日はもう仕事の話は無しだ」
「う…うん」
その夜――
「な、何だよ、これ……アタマ爆発する〜〜〜〜。
でも、あいつの手前、できませんでした…じゃ、カッコ悪すぎるよな。
くっそー、こうなったら徹夜だ徹夜〜〜〜!!」
翌日放課後――
「ほら、できたぜ」
ポルトスは、さわやかに笑ってダルタニアンに書類を渡した。
「ありがとう、ポルトス。大変だったでしょう?
寝不足になるんじゃないかと思って心配したけど、元気いっぱいでよかった」
「え…あ、ああ、睡眠なら十分だぜ。ほら、この通り絶好調だ」
(朝までかかって終わらせて、その後爆睡してさっき目が覚めた…なんて言えねぇ)
(朝までかかって終わらせて、その後爆睡してさっき目が覚めたんじゃないかな)
― Fin ―
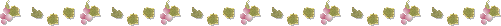
| GUIDE
| TEXT
| BOOK |